ハラスメントはもうこりごり!どう対応すればいい?介護職にまつわるハラスメントと対処方法!
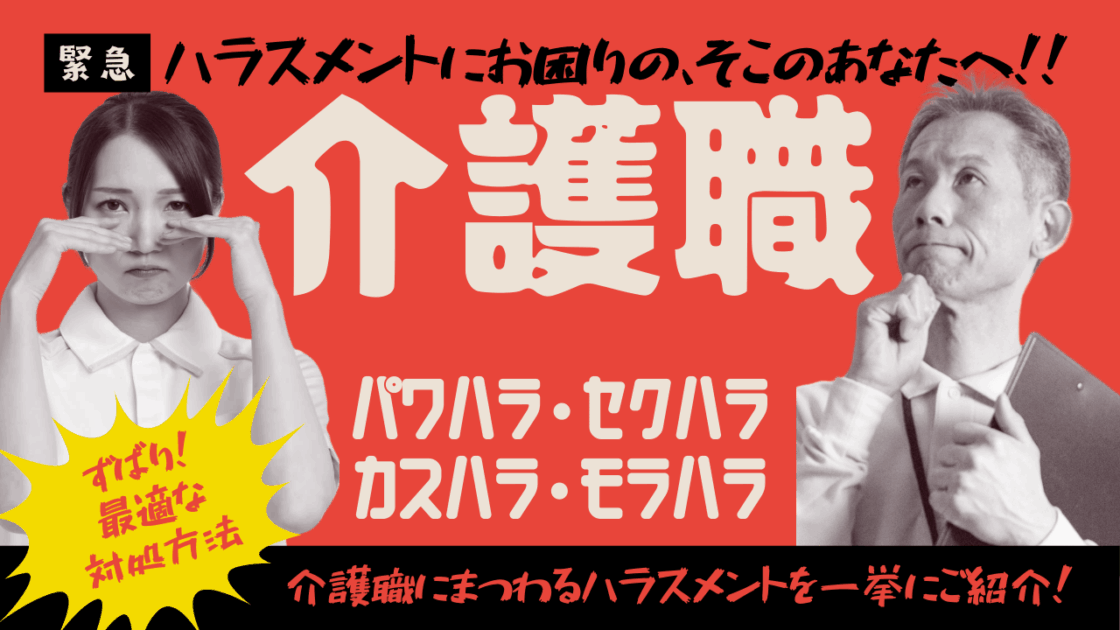
介護職はほかの職種と比べ、ハラスメントを受けやすい職業です。
- パワーハラスメント(パワハラ)
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
- モラルハラスメント(モラハラ)
職員・利用者・家族・様々な関係からのハラスメントが起こります。

ハラスメントを受けたことがあるけど、どうしたら良かったのの?



自分がしてることがハラスメントになってたらどうしよう。
ハラスメントを受けたときは、
記録を残して信頼できる人に相談しましょう。
記録は証拠として必要です。
必ず証拠を用意してから第三者に相談してください。
今回はそんなハラスメントに対する悩みを少しでも改善できるように、ハラスメント事案に役立つ情報や対策について紹介していきます。
1. 利用者・家族からのハラスメント
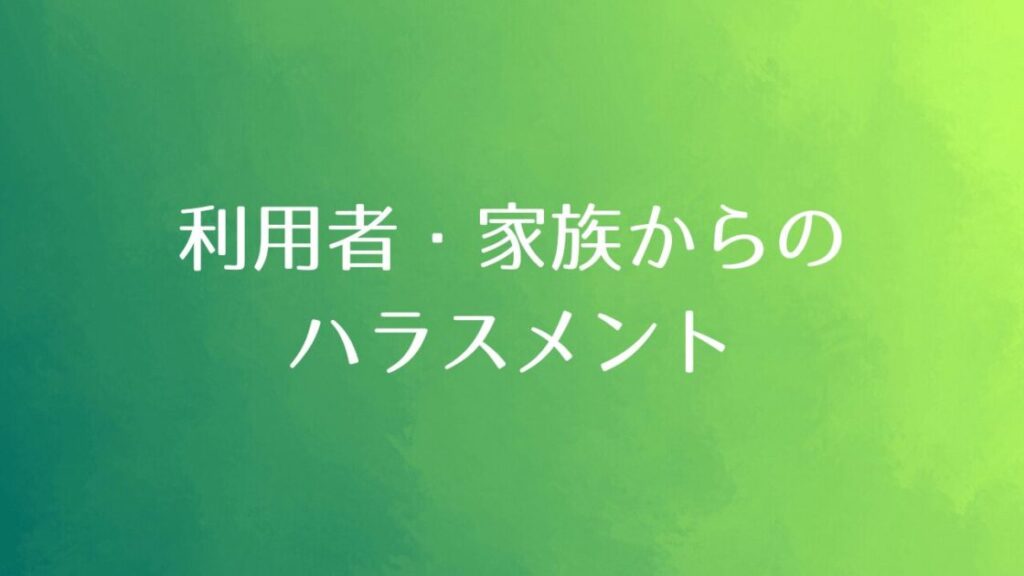
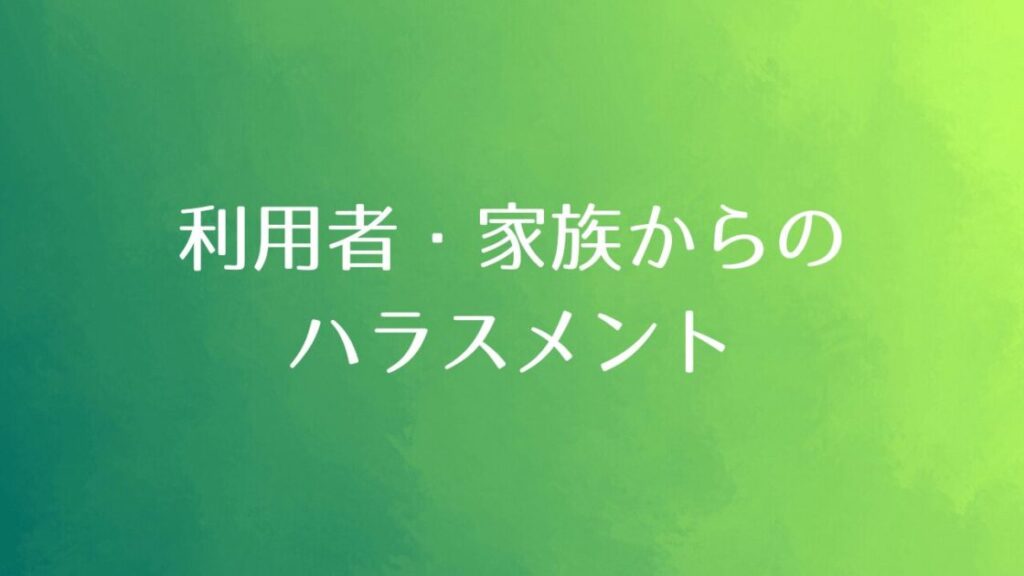
介護施設や訪問介護の現場では、利用者やその家族からのハラスメントの発生が少なくありません。



実際に私が経験したことがあるものも紹介します。
パワーハラスメント(パワハラ)
・暴言
利用者から「バカ」「役立たず」「仕事ができない」などの侮辱的な言葉を浴びせられることもあります。
認知症の症状の場合もありますが、その場合は時間を空けて声をかけたり、職員を変えたりして対応すれば対処できますが、認知症がない場合は別の対応が必要です。
・暴力
叩く、つねる、かみつく、物を投げるなどの身体的な攻撃を受けることもあります。
認知症の症状に暴力行為があります。利用者はかなりの力なので、高齢者だからと言って油断しているとケガをしてしまいます。認知症の症状でない場合でも、暴力行為を受けるケースがあるので気をつけましょう。
・威圧的な態度
大声で怒鳴る。執拗にクレームを入れる。
この場合は、主に家族からのものが多いです。「祖母をもっと歩かせて!」「どうして〇〇させないんですか?」と何度もクレームを受けることがあります。理由を説明しても納得されないことがよくありますね…
利用者で認知症の症状でない場合でも、怒鳴りつけられたりされることもあります。
介護未経験の新人職員の方がびっくりして、泣いてしまうことも…
- 認知症の利用者が介護士を叩いたり、噛みつく。
- 家族が「私の母をもっとリハビリさせて」と怒鳴り、長時間説教する。
- 利用者が介護士を杖で叩く。
認知症の症状で暴力的になることもあり、仕方ないことではありますが、職員側に問題がなければ上司と相談し、冷静に対応していかなければなりません。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
・契約外のサービス要求
掃除や買い物など、本来の介護サービスに含まれない業務を強要する。
介護士はすべての利用者を平等に対応しています。誰かを特別視することはできません。「うちの母のために○○してほし」と頼む際は、サービス範囲内なのか家族は確認しましょう。
・個人的な頼みごと
「自分の分の買い物をしてきてほしい」「家族の食事も作ってほしい」などの個人的なお願いをされる。
訪問介護の場合によくあります。サービス範囲外のことはできないです。
「してあげたい」とは思いますが、1つすると次から次にと頼みごとが増えていきます。
・金品の要求
「お金を貸してほしい」「お金をあげるから特別扱いしてほしい」などの依頼をされる。
はきはきした職員には言わず、断りずらそうな人に対してだけお願いされることがあります。
- 訪問介護の際に、利用者から「ついでに庭の掃除をしていって」と頼まれる。
- 家族から「親の介護をもっと丁寧にしてくれたら、お礼をする」と暗に賄賂を示唆される。
事業所ごとの規約を確認して対応しましょう。何度も繰り返す方には事業所から直接対応してもらうのが得策です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
・身体接触
手を握る、腕も掴む、胸やお尻を触る、抱きつく。
介助中であっても不必要に触ってきたり、介助時以外に「ねえちゃんもっとこっちにきて」と腕を引き寄せられることもあります。
・性的な発言
「若いからモテるだろう」「いい体してるね」など言われたり、「ここ触って」と手を掴まれ、陰部を触らせようとしてくることがあります。
- 男性利用者が、女性介護士のお尻や胸を触る。
- 入浴介助の際に、「あんたも服脱いで」と言われる。
- 排泄介助中に、「気持ちええことしようや」と言われ抱きつかれる。
セクハラのケースは本当に多いです。
利用者と同性の職員と対応を変わるか、すぐに離れて助けを呼びましょう。以外と軽く流して対応する職員もいますが、自分以外が被害を受けることを考えてください。
職場内のハラスメント
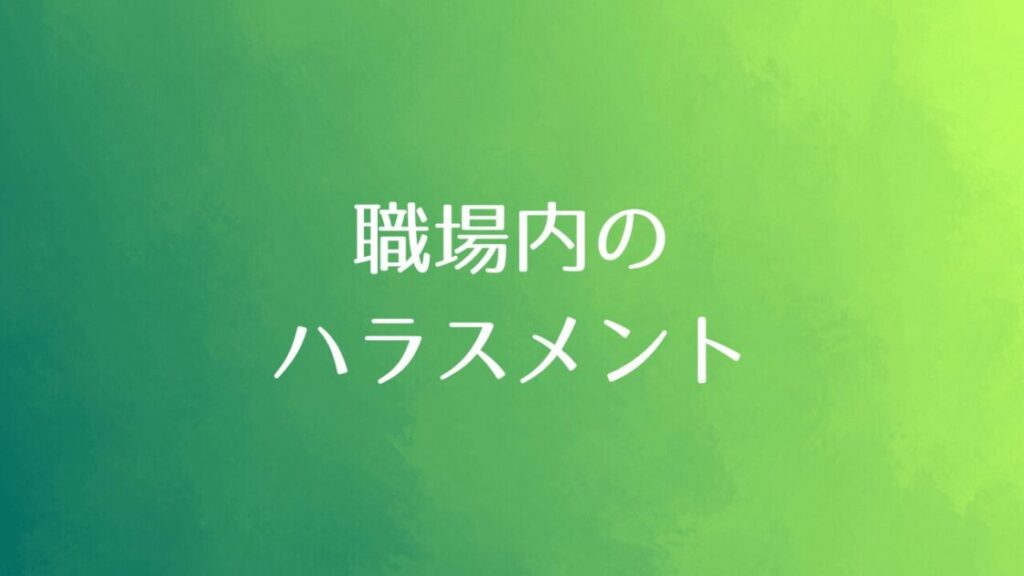
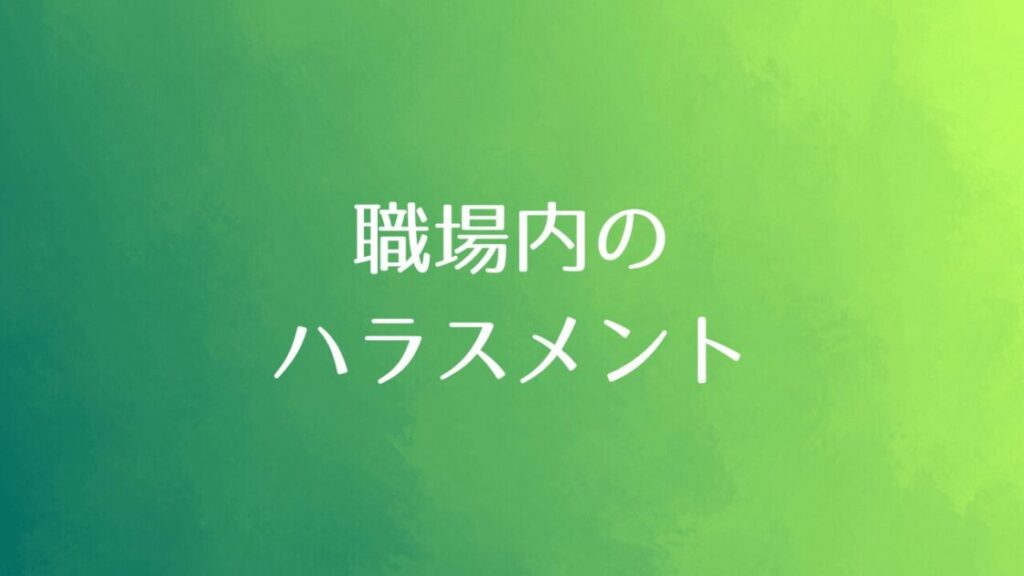
パワーハラスメント(パワハラ)
介護業界は上下関係が厳しく、パワハラが発生しやすい職場環境にあると言われています。
・人格否定
「こんな仕事もできないの?」「この仕事向いてないよ?」「バカだから仕方ない」など言われる。
・過重労働の強制
シフトを詰め込み、休ませない。
・退職強要
「この仕事が向いてないから辞めろ」と辞職に追い込む。
・業務妨害
必要な情報を共有しない。業務をわざと任せない。
- 上司が「黙って言われたことやれ」「こんなこともあなた達はできないの?」と高圧的な強い発言をする。
- 体調不良で休みを申し出ると、「人手不足なのに休むの?」と責められる。
- 私用で夜勤ができないと言っている職員に、「やってもらわないと困る。みんなはやってるよ?」と強制的に急な夜勤をさせる。
一緒に働いていて何度も聞いたことがあります。陰で泣いている姿も見かけたことがあります。
私の経験では、女性のベテラン職員に多いです。相手を思いやる気持ちと行動をしていただきたいものです。



私も言われた経験があるので、あの頃はほんとにつらかった…
モラルハラスメント(モラハラ)
日勤、早出、遅出、夜勤などの分担された勤務時間や業務分担をしている為、嫌がらせや陰口など、道徳や倫理に反した言動や態度による嫌がらせが起きやすいです。
・陰口・悪口
「あの人、仕事遅いよね」「すぐにミスするよね」など。
・無視・孤立させる
挨拶をしても返さない、情報共有をわざとしない。
・意図的な嫌がらせ
必要な物品や私物を隠す、重労働ばかり割り振る。
- 特定の職員にだけ冷たい態度を取り、無視をする。
- 「あの人と仕事が一緒だと終わらない」「もう辞めればいいのにね」と本人にも聞こえる場所で悪口を言う。
挨拶をしない職員が案外います。職員同士以外にも家族や利用者も無視する方もいましたが、考えられません。
人として基本的なことですので、あいさつは必ずしましょう。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
・性的な冗談・発言
「制服似合ってるね」「今日も可愛いね」と発言する。
・身体への接触
肩を触ったり、腰に手を回される。
- 施設長が、若い女性職員にだけボディタッチをする。
- 「結婚しないの?彼氏はいるの?」など、プライベートな話をしつこく聞く。
年配の職員に多いですね。時代を考えた行動をしましょう。
エイジハラスメント(エイハラ)
相手の特徴を無視して、年齢や年代にだけ注目して、差別的な発言や対応をすることです。
幅広い年代が働く介護現場では頻繁に見かけます。
・若手への偏見
「最近の若い子は根性がない」「若い子なのにスタミナがない」などの発言。
・ベテランへの偏見
「年寄りには無理な仕事だからやらなくていい」「歳とってるから物知りですね」などの発言。
- 新人職員に対して「若いんだからもっと動いて」と言っている。
- 50代の職員が、「もう年だからこの仕事は無理でしょう」と決めつけられる。
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
・性別に基づく偏見
「男なのに介護士なんて情けない」「女は体力がないからダメ」などの発言。
- 男性介護士が「女性の入浴介助はできないだろう」と決めつけられる。
- 女性介護士が「力仕事は男性に任せて」と言われる。
マタニティハラスメント(マタハラ)
・妊娠・出産を理由にした嫌がらせ
「妊婦なのに仕事を続けるなんて迷惑」「まだお腹出てないから力仕事できるよね」と発言。
・産休・育休の取得への圧力
「休むと人手が足りなくなる」「あの人、まだ育休取ってるの?」
- 妊娠を報告した途端、「そのまま辞めたほうがいいんじゃない?」と言われる。
- 復帰後、産休前のような重要な仕事を一切任せてもらえなくなる。
最近ではあまり見かけなくなってきましたが、昔に見かけたことがありました。育休で休んでもその人の能力は変わりません。
介護士がハラスメントを受けた場合の対策
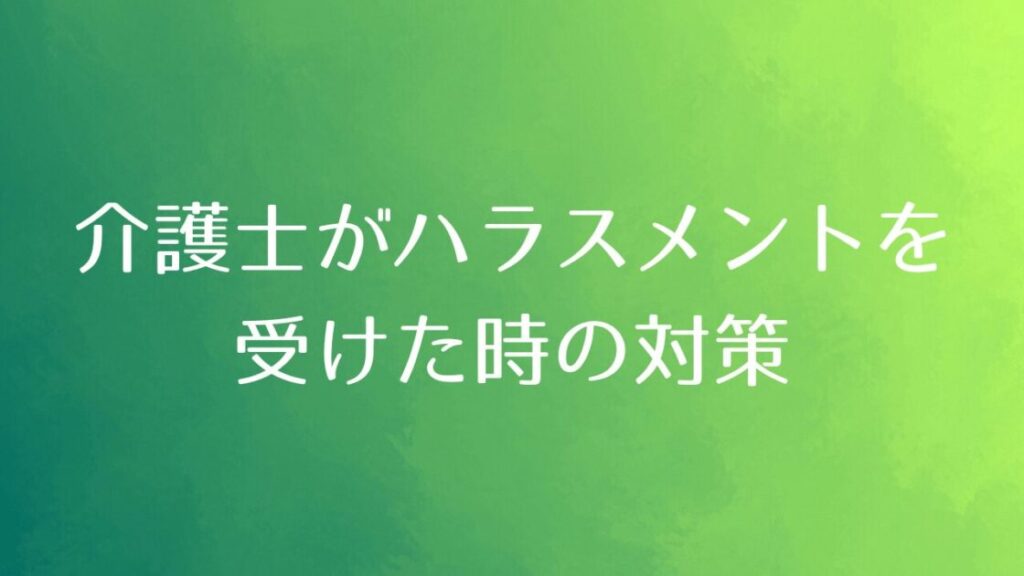
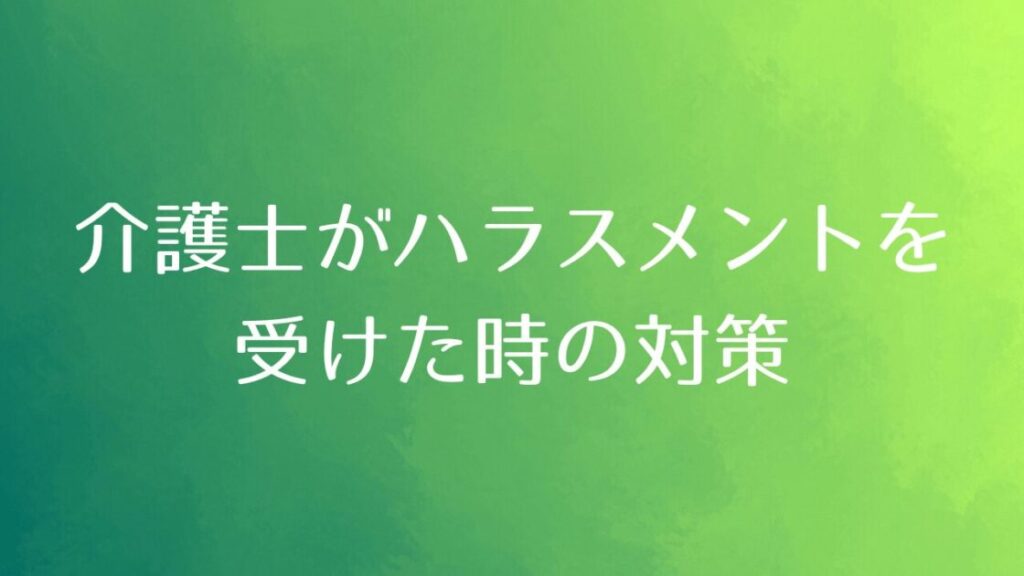
では、ハラスメントを受けた際はどのように対応するべきなのでしょうか。
厚生労働省が作成したマニュアルとハラスメント事例集を見てみましょう。
- 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
厚生労働省が作成したマニュアルで、介護現場でのハラスメントの実態や対策が詳しく解説されています。
mhlw.go.jp - 介護現場におけるハラスメント事例集
具体的な事例を通じて、ハラスメントの発生状況や対応策を学ぶことができます。
mhlw.go.jp
このなかでは「1人で抱え込まない」ことと明記されています。
どうしても人と人との関係で起きてしまうトラブル故に、「私が悪かった」「私に落ち度があった」と、1人で抱え込みすぎてしまい、誰にも相談ができない、助けを求められない状態になりがちです。
あなたの周りには必ず助けてくれる方がいますし、助けられるような仕組みが存在します。
相談窓口も設置されているので、勇気をもって相談することが大切です。



相談しやすいように、管理職には男性と女性が配置されていることがあります。



ハラスメントを受けたらすぐに相談すればいいの?



すぐに相談することも大切ですが、相談する前にしておいたほうがいいこともあります!
(1) 記録を残す
・日時・内容をメモして証拠を確保する。
証拠を確保しておくことはとても大切です。
ハラスメントの発言者が事実を否認したり、記憶違いを主張することがよくあります。証拠があれば、事実関係を明確にし、客観的な判断が可能になるからです。
また、社内の相談窓口や労働局、弁護士などに相談する際に対応してもらいやすくなります。
「いつ」「どこで」「だれから」「どのようなことをされたのか」をしっかり記録して残しておきましょう。
・録音・スクリーンショットを活用する。
相手から、「そんなことはいっていない」と言い逃れされないように、ボイスメモなどで録音しておくことも大事です。
裁判や労働審判を行うことになった場合にも、主張の裏付けになり有利に進められます。



私の知り合いにも実際に録音していた方がいました。
音声を聞くまでは(ほんとかな?)と疑っていましたが、実際に聞かせてもらうと背筋が凍りました…
(2) 相談する
誰かに相談することには勇気が必要ですが、自分の身を守ること・ほかの被害者をださない為に勇気をもって相談してみましょう。
- 職場の上司・管理者に報告
- 労働基準監督署、介護業界の相談窓口を活用する
(3) 法的対応も視野に入れる
・弁護士や労働組合に相談し、法的手段を検討する。
自分の権利を守る・職場環境の改善・慰謝料や損害賠償を請求・心理的な負担が軽減されるなどのメリットもあるので、慎重に検討しましょう。
しかし、注意点も存在します。
(4) 万が一のリスクや注意点
相談すること・訴えることにはリスクも伴います。
・報復を受ける可能性
陰口や誹謗中傷をされたり、仲間外れや不利益な扱いを受けることがあります。
・精神的・経済的な負担
噂が広まり、同じ業界内での再就職が不利に働いたり、ご近所さんや地域の方から精神的なストレスを受けることも考えられます。
介護士は利用者や職場内の人間関係でハラスメントを受けやすい立場ですが、決して泣き寝入りせず、適切な対応を取ることが重要です。
あってはならないことですが、リスクを頭に入れておくことも自分の身を守ることにつながります。
まとめ


みんなの介護というサイトでは、介護職員を守るための取り組みがあります。
介護現場のハラスメント実態と対策。職員を守る3つの取り組み
介護現場でのハラスメントの種類や具体的な事例、そして職員を守るための取り組みについて解説されています。job.minnanokaigo.com
ハラスメントに遭遇しても、冷静に対処していきましょう。
今回の記事で、ハラスメントに悩んでいる介護士の方が少しでも救われ、現状が改善することを願っています。
もし、あなたの周りに相談できる人がいなければ、お問い合わせにご相談ください。些細なことでも大丈夫です。



最後まで読んでいただきありがとうございました。





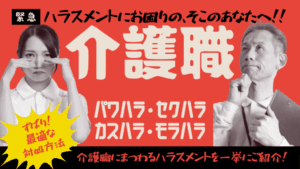




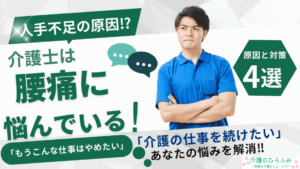

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] […]