特別養護老人ホームの仕事内容とは? 特養と老健の違いを比較しながら徹底解説!

「特別養護老人ホーム(特養)」と「介護老人保健施設(老健)」の違いについて気になったことはありませんか?
特養と老健はどちらも高齢者向けの介護施設ですが、役割や仕事内容、働き方には大きな違いがあります。
ズバリそれは、
特養は要介護3以上で長期間入所する施設で、日常生活の介護が中心。
一方、老健は在宅復帰を目指す施設であり、リハビリが中心。
では特養の仕事内容はどのようなものなのか?
そして、老健との違いはなにか?
今回の記事は、
特養と老健の違いを比較しながら、特養での仕事内容や働くメリット・デメリットをご紹介していきます。
特養への転職を考えている方や、老健からの転職を検討している方はぜひご参考ください。

1. 特別養護老人ホーム(特養)とは? 老健との違いをわかりやすく解説!

まずは施設そのものの違いを解説します。
基本的な違いを知ることで、自分は特養に向いているのか明確になるでしょう。
特養と老健の基本的な役割とは?
どちらも介護が必要な高齢者が利用する施設ですが、役割には大きな違いがあります。
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 介護度が高く、在宅生活が困難な高齢者が入所する施設
- 基本的に終の棲家として、長期間の入居が可能
- 生活支援や介護が中心で、リハビリは老健ほど重視されない
- 原則65歳以上の要介護3以上
- 老健(介護老人保健施設)
- 介護とリハビリを組み合わせた「在宅復帰」を目的とする施設
- 3〜6か月の短期入所が基本(必要に応じて延長も可能)
- 介護職・看護職に加えて、理学療法士や作業療法士が多く在籍し、リハビリが充実
- 原則要介護1以上

こうやって見ると全然違う施設なんだね。



ポイントは要介護度と入居期間、そしてリハビリだね
介護施設の種類の中での特養と老健の位置づけ
介護施設には、特養や老健のほかにも「グループホーム」「介護付き有料老人ホーム」などがあります。それぞれの特徴を簡単にまとめると次のようになります。
| 施設名 | 目的 | 入所期間 | 介護度 |
| 特養 | 長期入所・生活支援 | 基本的に終身 | 要介護3以上 |
| 老健 | 在宅復帰支援 | 3~6か月(延長可) | 要介護1以上 |
| グループホーム | 認知症高齢者の共同生活 | 長期 | 要支援2以上 |
| 介護付き有料老人ホーム | 民間運営の介護施設 | 長期 | 要支援1以上 |



特養は要介護度が1番高いんだね。



そうなんです。
高齢になるほど、表の上側の施設を利用する傾向にあります。
特養は入居待機者が非常に多いです。
短い場合は数か月ですが、地域によっては数年待機することがあります。



私の地域では7年程入居を待たれている方がいました。
2. 特養と老健の入居条件・利用期間・費用の違いとは?


ここからは入居条件・利用期間・おおよその費用を比べていきましょう。
特養の入居条件と費用の目安
特養に入るには、原則として65歳以上で要介護3以上の認定を受けている必要があります。
また、40〜64歳の方でも特定16疾病を患っている場合に限り入居可能。
- 月額費用の目安:7万円~15万円(介護保険自己負担分・食費・居住費込み)
- 所得が低い方は補助制度あり(「介護保険負担限度額認定」により減額される場合も)
- 認知症の暴力行為がある際は入居を断るケースもある



入所になってからも、暴力・セクハラ行為がある場合は退所になる場合があります。
老健の利用条件と費用の違い
老健は要介護1以上であれば利用可能ですが、原則として自宅復帰を前提とした短期利用が基本です。
また、特養と同じように40〜64歳の方でも特定16疾病を患っている場合に限り入居可能。
- 月額費用の目安:8万円~15万円
- 医療ケアやリハビリが充実しているため、医療費がかかるケースもある
月額費用に関しては、特養・老健ともに自己負担額で変わるので目安程度として覚えてください。
特養と老健、どちらがどんな人に向いている?
- 特養が向いている人:
- 介護度が高く、長期間の入所が必要
- 終の棲家として安心できる環境を求めている
- 老健が向いている人:
- 退院後、自宅復帰を目指してリハビリを受けたい
- 期間限定で介護サービスを受けながら体調を整えたい
こうやって見比べると、利用目的の違いがよくわかりますね。
自宅に帰りたいのか、ゆっくり過ごせる場所があればいいのか。



「老健にずっと居られる」「特養でリハビリを受けられる」と勘違いで利用するケースも経験したことがあります。
3. 特養の仕事内容とは? 介護職の1日の流れと主な業務内容


では実際の特養の仕事内容についてみていきましょう!
特養の介護職の1日のスケジュール
特養では、利用者の生活支援が中心となるため、業務内容も日常生活のサポートがメインです。
専門的なリハビリがないためレクリエーションや行事等のイベントが午前午後に組み込まれています。
| 時間帯 | 主な業務 |
| 7:00~9:00 | 起床介助、朝食介助、口腔ケア |
| 9:00~12:00 | 排泄介助、入浴介助、レクリエーション準備 |
| 12:00~13:00 | 昼食介助、服薬管理 |
| 13:00~15:00 | 休憩、レクリエーションや個別ケア |
| 15:00~18:00 | おやつ、排泄介助、夕食準備・介助 |
| 18:00~21:00 | 就寝介助、記録業務、巡回 |
| 21:00~翌6:00 | 夜勤業務(巡視・排泄介助・体位変換) |
1日の流れに関しては施設ごとに違いますので、あくまで参考程度に捉えてください。



ICT機器の導入によって記録業務やナースコール対応がスムーズになりつつあるため、空いた時間で個別ケアを行うことができます。
食事・入浴・排泄介助の具体的な仕事内容
介助自体の方法は特養も老健も変わりません。
その分、老健から特養に転職をしても仕事の内容に困ることなく始められます。
ただ介護度が高い方が多いので、介助自体の時間は長くなり身体的な負担も大きいです。
- 食事介助:利用者さんの状態に合わせて、食形態(普通食・刻み食・ミキサー食など)を調整しながら提供。
- 入浴介助:週2回以上の入浴介助を行い、清潔を保つ。
- 排泄介助:オムツ交換やトイレ誘導を行い、快適な生活をサポート。



施設によっては腰痛予防のためにコルセットを支給してくれます。
レクリエーションや生活支援の役割
特養では、利用者さんが楽しく生活できるよう、レクリエーションや季節ごとのイベントが盛りだくさんです。
大勢が苦手な方にも楽しんでいただけるように少人数のグループに分かれて作品作りに取り組んでいただいたり、
四季を楽しめるようなドライブや、散歩、正月にはお餅を一緒に作って食べるのもとても楽しめます。
老健でもレクリエーションや行事は行われますが、リハビリを重視した内容になっていますね。



どちらの施設もレクリエーションや行事も盛り上がって楽しいことは変わりありません。
4. 特養と老健の仕事内容の違いを比較! 介護の負担やスキルの違いとは?


老健と特養の介護度の違いが仕事に与える影響
老健は自立度の高い方が多く、リハビリが中心です。もちろん医療的ケアのために入居されている方もいます。
トイレに行かれる方(トイレ誘導)、歩いて入浴される方(一般浴)が仕事として多いです。
一方、特養は介護度が高いため、身体介護の負担が大きくなる傾向があります。
食事・排泄・入浴の介助は、時間と腰の負担が増加。よって腰痛を訴える職員も少なくありません。
特養では看取り介護も重要な業務
看取りとは、延命治療を行わず、自然な最期を迎えられるまでサポートすることです。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査では特養で看取りを受け入れている施設は87.9%、受け入れてない施設は9.2%の割合になっています。
「看取り介護に興味があって特養に勤務することを決めたのに受け入れていなかった」ということが無いように
特養に勤務を望む方は、看取りを行っているか確認してみましょう。
5. 特養の利用者の特徴は? 老健と比べた介護度やケアの違い


特養の利用者の平均介護度と身体状態
おさらいですが、特養の利用者の多くは要介護3~5で、身体介護の支援が必要な方が多いです。
しかし、ショートステイで利用される方には要介護1~2の方もいます。
あわせて平均介護度は3~4と言えるでしょう。
寝たきりの方や、車いすに乗ることに介助が必要な方も多いです。
認知症やその他の病気でうまく思いを伝えられない方には、言葉以外のコミュニケーションも必要になってきます。



近年では要介護3・4でも動きのアクティブな方が増えているのが印象的です。
特養で必要とされる介護技術とは?
特養では、排泄介助・入浴介助・食事介助などのスキルに加え、認知症ケアやターミナルケアの知識も求められます。
介護度が高い方が多いため体力も必要です。
そしてショートステイでは介護度の低い方や重度の認知症の方もいるため、幅広い介護スキルが必要になります。
夜勤中では介護士のみになるので、看護師に連絡する前に介護士の判断力や対応力が重要になってきます。
老健と比較した際の職場環境の違い
老健との職場環境の違いを3つにまとめてみましょう。
- 老健はリハビリ中心で、比較的自立度が高い利用者が多い
- 特養は生活介護が中心で、身体介助の頻度が高い
- 夜勤の負担は特養の方が大きいが、利用者との関係性を深めやすい



リハビリ支援の老健もいいけど、特養も魅力的だな~。



私の印象では、老健は「自宅復帰」を目標にした利用者さんなので活力にあふれている印象です。
そして特養は落ち着いたのんびりとしたライフスタイルの方が多いです。
6. 特養で働くメリット・デメリット 老健との違いを踏まえて解説


特養で働くメリットは何がある?
老健で働くメリット!
- 職員と利用者の間に深い信頼関係が築ける
- 公的な運営が多く、給与や福利厚生が充実
- 老健に比べて急な利用者の入れ替わりが少なく、落ち着いた環境で働ける
長期的なケアを通じて、一人ひとりの生活に寄り添った介護ができるため、やりがいを感じやすい環境といえます。
働く上で給与や福利厚生が充実しているのは嬉しいポイントですね。
やりがいがあるからと言って、安月給ではモチベーションに響くと思います。



深い信頼関係っていいな~



逆に深くなりすぎて、聞いちゃいけないような家族の話をされて困ることもあります笑
特養での課題やデメリット
特養で働くデメリット!
- 看取り介護が精神的な負担が大きい
- 24時間体制のため、体の負担も大きい
メリットにある信頼関係が深くなることが、辛さをより増加させてしまいます。
利用者の最期に寄り添うことは非常に重要な仕事ですが、感情的に辛いと感じる職員少なくありません。
肉体的な負担として、重度の要介護者が多いため夜間の見守りや介助の負担があります。
夜勤の回数やシフト体制は施設によって異なりますが、体力的な負担を感じることも少なくありません。



コルセットを支給する施設もありますが、それだけ腰に負担がくるということですね。
人手不足の影響もあると感じます。
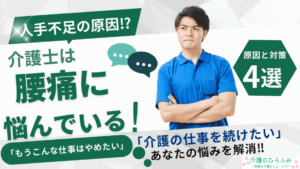
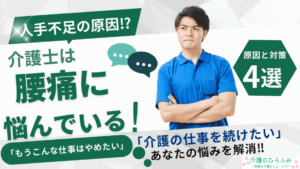
老健と比較した際の職場環境の違い
老健と比較すると、特養は利用者の入れ替わりが少なく、長期的な関係を築けることが特徴です。
老健ではリハビリを重視し、在宅復帰を支援する業務が中心ですが、特養では日常生活の介助がメインとなります。
また、老健では医療職のスタッフと連携する機会が多いのに対し、特養では介護職が中心となって連携したケアを提供する場面が多くなります。
そのため、介護職として主体的に動ける環境を求める人にとっては、特養のほうが適している場合もあります。
7. 特養の職員配置とチームケアの仕組み


特養では、介護職員・看護職員・ケアマネ・生活相談員・機能訓練指導員などが連携しながらチームケアを提供します。
日中は複数のスタッフがいるため、わからないことや疑問に感じたことはすぐに確認できるので介護に初めて携わる方でも安心して働けます。
介護職員の配置は特養も老健も利用者3人に対して1人以上です。
ただ、老健はその内の7分の2が看護師になります。
8. 特養への転職を考えるなら? 事前に知っておくべきポイント


特養に向いている人の特徴とは?
特養向きな方の特徴!
- じっくりと寄り添った介護をしたい人
- 利用者の人生の最期を支えることにやりがいを感じる人
- 体力的・精神的にタフな人
- 安定した環境で働きながらも、長期間にわたるケアを提供したい人
逆に、自宅復帰に向かって頑張る背中を押したい人やリハビリにも興味がある人は老健に向いています。
どちらが自分に合っているのかを想像することで、介護の方向性が見えてくるでしょう。



正直、老健から特養に転職した私ですが自分に合っていた施設は老健だと感じれました。
実際に働いてみることでわかる良さもありますね。
特養への転職でチェックすべきポイント(求人の見方・職場環境)
特養の求人を探す際は、まず「職員の配置基準」や「夜勤の回数」「給与・福利厚生」をチェックしましょう。
施設によってシフトや業務負担が異なるため、自分の軸を決めてから職場を選ぶことが重要です。
また、施設の雰囲気や職場環境も重要なポイントです。
可能であれば見学をして、職員同士の関係性や働きやすさを確認するとよいでしょう。
まとめ
今回は特別養護老人ホームについて、介護老人保健施設と比べることで想像することができたと思います。
落ち着いた環境の中で利用者さんとじっくりと向き合う介護の魅力は、介護福祉士を取得したあなたに介護の幅広さを教えてくれるでしょう。
あなたが老健で培った「リハビリ知識」や「医療職との連携スキル」は特養でも活きてきます。
身に付けてきた技術とスキルは決して裏切りません。
四季の移ろいを一緒に楽しみ、日常生活の支えとなる介護を始めましょう!



最後まで読んでいただきありがとうございました。



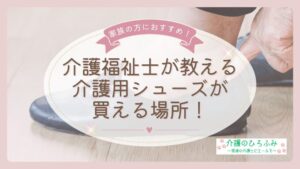


コメント